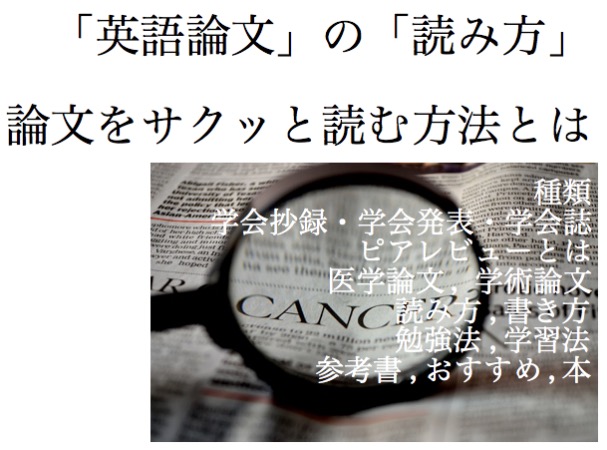インターネットの発達ともに、様々な情報が氾濫しています。
その中には、医学・法律・お金に関する情報のように、
情報の質が極めて重要なものもございます。
そういった中で、情報の質を検証しながら読む姿勢がますます求められています。
情報の質を担保する方法の1つは、信頼のおける情報源を持つことです。
「学術論文」は、信頼性の高い情報源の1つです。
学術論文の多くは、英語で書かれた「英語論文」になります。
英語論文を読みこなすことで、
信頼のおける確率の高い情報を得ることができます。
一般の方も、英語論文を読めればいいなぁという機会が増えているのではないでしょうか。
しかし、英語論文を読むことにハードルが高いと感じる方も多いのではないでしょうか。
でもだいじょうぶです。
本ブログではこれまでに、
英語論文をサクッと読めるようになるために、
以下の記事をまとめてきました↓
- 英語論文に頻出する「英単語」を攻略したいあなたはこちら↓
『医学論文の英語の単語を学びたいあなたにおすすめの勉強法や本、辞書はこちらです』
- 英語学術論文に頻出する「使える英語表現」を知っておくと読み・書きやすくなります↓
『「英語論文」の「使える表現」を学んで、学術論文をサクッと読み書きしたいあなたはこちらをどうぞ』
- 英語論文の構成を知ることで、サクッと読み書きできます↓
『「英語論文」の「構成」とは?テンプレートやフォーマットを学び、効率的に読み・書きしたいあなたはこちらをどうぞ』
- 論文内容をサクッと要約して理解できる方法「PECO(または PICO)」について↓
『『「医学論文」の読み方で役立つ「PECO」とは?PECOの使い方や注意点もまとめました』』
本記事では、これらの内容を踏まえながら、
より実践的な英語論文の読み方をご紹介します。
本記事の概要
「英語論文」の「読み方」とは?医学論文など学術論文をサクッと読みたいあなたはこちらをどうぞ
英語論文の読み方のポイント
英語論文を効率的に読むには、
- 論文の構成を知っておくこと
が役立ちます。
さらに、以下の2点に気をつけることがポイントです。
- 英語論文の各部分を読む「順番」
- 英語論文の構成の「各部分の読み方」
このうち、各部分を読む順番については、
あなたがその分野にどのくらい前提知識などがあるかによって変わってきます。
- その論文の専門外の方
- その論文の分野の専門家の方
では、読み方はまったく違います。
また専門家の方であれば、ここで読み方を学ばなくても、すでに読みなれておられるかと思います。
なので、ここでは、
- 英語論文をほとんど読んだことがない
- 英語論文を効率的に読めるようになりたい
- 「専門外」の内容を読んでいる
といったあなたが、より効率的に、サクッと読めるようになる
英語論文の読み方の1例をご紹介します。
初心者が英語論文をサクッと読み方法
英語論文をサクッと読むには、「適切な順番」があります。
論文内容はボリュームがあるものも多いですから、
専門外の方が、すべてを読解しようとすると、膨大な時間がかかります。
なので、論文の構成を意識しておき、
読んでいく順番を把握しておくことが役立ちます。
まずは論文の全体像をつかむことが大事
全体像をサクッとつかむためには、
- タイトル
- 抄録・要約(アブスト)
を読んでいきます。
アブストの中から、対象、方法、結果、結論、の4つを把握することが重要です。
これだけで、論文の骨格を理解できたことになります。
その後は、論文の中で、自分が知りたい情報がある部分をできるだけ絞りながら読み進めていきます。
目的を持って読んでいく、とも言えます。
例えば、男性に対しての研究結果を知りたければ、
- 研究対象の部分に男性が含まれているか確認する
- 男性についての結果を読む
- 比較対象(この場合女性)と、どう違ったのか
- 結論部分で、男性についてどのように結論づけられているか
といった点を読み解いていて、
それらをつなげることで、知りたい情報について、
論文から得られる内容の理解が深まるかと思います。
英語論文を読むのに慣れてきたら、
関連論文も合わせて読んでみるのもおすすめです。
理由は、その論文内容をより深く理解できるからです。
そこで、関連論文の探し方や読み方の1例をご紹介します↓
関連論文の探し方・読み方とは
学術論文の本文では、
関連する他の論文(参考文献)がある箇所には、番号(もしくは第1著者名)が示されます。
本文中の詳しく知りたい箇所にある参考文献の番号をメモしておきます。
次に論文の最後を見ると、文献のエリアがあります。
文献エリアには、関連論文のリストが番号順(アルファベット順の場合もあります)に並べられています。
メモした文献の番号(または著者名のアルファベット)を見て、
関連論文の雑誌名や巻・号・ページなどを確認します。
関連論文の情報を得たら、
その学術雑誌のサイトに行き、巻・号・ページを入力して
関連論文を得ます。
他の探し方としては、
関連論文のタイトルをそのままグーグル検索する方法もあります。
グーグルに登録されていれば、検索上位ページに関連論文のあるサイトへのリンクが見つかります。
関連論文を読むときのポイント
関連論文が手に入ったら
元の論文との違いに注目して
読んでいきましょう。
こうすることで、元論文よりもさらに効率的に読めます。
例えば、元論文の結果について、
- 手法によって結果が変わることはあるのか?
を知りたければ、
同じ内容を違う方法で調べた関連論文を探します。
そして、結果の手法依存性を確認するには、
主に結果と結論を確認すればいいので、
そこだけチェックすればいい、となります。
このように関連論文を読むときには、
目的をはっきりさせて、必要な情報だけピンポイントに読むことがポイントになります。
加えて、結果として、元の論文についての理解をより深めることもできます。
さらに英語論文の読解力を高めるには
興味ある論文と、その関連論文を読めれば、
初心者の方や、一般の方は、
おおよそ知りたいことを知れるのではないでしょうか。
さらに専門家に近づくには、
- 手法について詳しく学ぶ
- 背景知識を学んでいく
といったことを積み上げていくことになります。
例えば、医学論文では、手法として統計解析が用いられることが多いです。
医学論文をより正確に読みたいあなたは、以下の記事もどうぞ↓
『「医療統計」を基礎から入門したいあなたにおすすめの良書、8冊はこちらです』
ここまでで、
英語論文の効率的な読み方の流れや順番をご紹介しました。
ここからは、英語論文の構成の各部分のそれぞれの読み方について、
- 何に注目するといいか
- どんな点に気をつけるといいか
といった点をご紹介します。
1, タイトル
タイトルには、以下の目的があります。
- 研究内容に重要なポイントが伝わる
- できるだけ多くの方に読まれるように興味を引くもの
- 理論や実験方法を書いて、読み手が調べる手間を省く
学術論文は読んでもらってナンボな面があります。
なので、
- 少しオーバーな表現
- 抽象的な表現
- より広範囲の研究があるかのような表現
がある場合もあります。
タイトルだけで鵜呑みにせずに、
本文と照らし合わせながら確認していくのが大事です。
2, 抄録・要約(abstract:アブスト)
抄録・要約は、論文の全体像をサクッとつかむのに使います。
また、この論文の詳細を読むかどうか判断材料にします。
アブストは、どの学術論文でも投稿規定で文字数が決まっており、
その文字数に収まるように、研究の背景・方法・結果・結論が凝縮されています。
なので、まずアブストをチェックすることで、
その論文の全体像をつかみ、
詳しく読むかを判断することができます。
3, はじめに・緒言(Introduction)
ここでは研究背景がまとめられています。
過去の研究をまとめながら、
その論文での研究目的を示されます。
- 過去にどこまで明らかになっているか
- この研究では何を明らかにするか
こういった点に気をつけながら読むのがポイントです。
この研究目的をしっかりつかんでおくことはとても重要ですので、丁寧に把握するようにしましょう。
研究目的は、イントロの最後の方のパラグラフ(段落)に書かれていることが多いです。
4, 対象と方法(Material and Method)
ここでは、研究した対象と、研究の方法がまとめられています。
- 同じ分野の専門家が読めば再現できるくらいの内容が書かれる
- 教科書レベルのことなどは書かれない
といった特徴があります。
学術雑誌の限られたページの中で、
専門家向けに必要最小限の情報が書かれています。
なので、この部分だけで、専門外の方が研究方法を正確に理解するのは無理だと思います。
なので、研究方法についてきちんと理解したい場合には、
別途、手法についての解説された教科書や書籍などで補うとよいかと思います。(ただし専門的な内容ですので、時間的にも内容的にもハードルは高くなります)
5, 結果(Result)
その研究で得られた結果がまとめられています。
まとめ方には、文章で伝えたり、図や表で伝えるやり方があります。
学術雑誌の限られた紙面を有効に使うため、
- 文章で示した結果は、図や表にはしない
- 図や表で示された結果は文章で書かない
のように内容が冗長にならないように配慮されています。
なので、文章と図表を適宜参照しながら読んでいきましょう。
文章だけとか、図表だけ読むとすると理解が偏ってしまう可能性があります。
ちなみに、結果で述べられる内容は、すべての研究結果ではなく、
論文の主張について重要な内容がまとめられています。
(結果に述べられない実験結果などもあります)
6, 考察(Discussion)
考察では、結果を踏まえて、
- 他論文との関連や比較
- 今回の研究方法の適用範囲や限界
- 今後の展望
などがまとめられています。
結果の部分は客観的な記述がほとんどですが、
考察には主観的な記述が加わってくることがあります。
考察を読み解くには、背景知識が必要となります。
背景知識を補うには、まずその論文のイントロを読んでみましょう。
イントロに加えて、参考文献を引いて読んでいくと理解が深まります。
それでもなお、専門外の方からすると、論理の飛躍が感じられる場合もありえます。
その場合には、専門家の中では当たり前すぎて書かれない内容が使われている場合も(ごく稀に)あります。
7, 結論(Conclusion)
結論には、研究で得られら成果と主張がまとめられています。
結論は、アブストにも短く書かれていますが、
結論では、成果と主張がより具体的にしっかりとまとめられています。
アブストの結論部分がわかりにくい場合には、
本文中の結論の部分を読んでみると理解できる場合があります。
8, 謝辞(Acknowledgement)
謝辞には研究を進める上で、協力いただいた方が書かれています。
- 助言や指導をいただいた方
- 研究試料・機器などでお世話になった方
- 論文原稿をレビューしてもらった方
などが書かれることが多いです。
また研究資金の出資元も書かれます。
9, 文献(Reference)
文献では、研究で参考にした文献のリストがまとめられています。
文献には、一般的に
- 過去の学術論文
- 学会抄録
- 書籍
- (場合によっては)インターネットサイト
といったものなどが含まれます。
その論文で厳密に述べられない部分は、参考文献に書かれている場合も多く、
その分野をきちんと理解しようと思ったら、
関連文献を引いて読んでいくことはとても重要になります。
文献とは?について知りたい場合にはこちら↓
『「学術論文」とは?文献や学術雑誌との違いについてまとめました』
付録(Appendix)
このほかに、
理論の論文などでは、数式展開や証明などが、
付録(Appendix)として付け加えられる場合があります。
付録は、8, 謝辞(Acknowledgement) と 9, 文献( Reference) の間に書くことが多いです。
というわけで、
本記事では、
英語論文の構成を活用した、
より実践的な英語論文の読み方をご紹介しました。
期間限定の2ヶ月無料で学べるオーディオブックもございます↓
こちらもございます↓
こちらもございます↓
『「医療統計」を基礎から入門したいあなたにおすすめの良書、8冊はこちらです』
『「医学論文」の読み方で役立つ「PECO」とは?PECOの使い方や注意点もまとめました』
『「英語論文」の「構成」とは?テンプレートやフォーマットを学び、効率的に読み・書きしたいあなたはこちらをどうぞ』
『医学論文の英語の単語を学びたいあなたにおすすめの勉強法や本、辞書はこちらです』
『「英語論文」の「使える表現」を学んで、学術論文をサクッと読み書きしたいあなたはこちらをどうぞ』