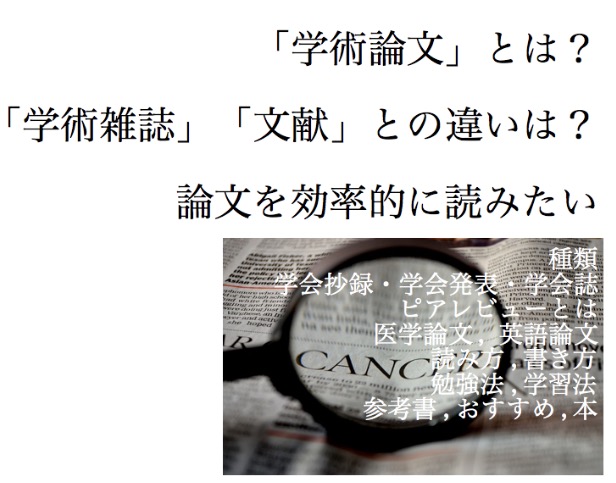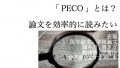毎日数多くの学術論文が出版されています。
科学の進歩は、これらの学術論文の積み上げによってなされています。
そういった中で、
- 科学情報に興味のある一般の方
- 科学関係を学んでいる学生の方
- 科学技術の関係者の方
など、日々忙しい中で、
- 学術論文を探す
- 学術論文を読む
- 学術論文を理解する
といったことが必要な方も多いんじゃないでしょうか。
そういった方は、まず
- そもそも学術論文ってなに?
- 学術論文にはどんな種類があるの?
- 文献や学術雑誌とはどう違うの?
といったことを知っておくことが役立ちます。
そこで本記事では、
学術論文をより効率的に探し、読み、理解したいあなたのために、
- 学術論文とは
- 学術論文の種類
- 文献や学術雑誌などの違い
など、研究の世界の約束事・基本ルールについての基礎知識をまとめたいと思います。
本記事の概要
「学術論文」とは?文献や学術雑誌との違いについてまとめました
学術論文とは
「学術論文」とは、学術的な内容を書いた「論文」になります。
「学術」とは学問のことです。
「論文」とは、
一定の成果を上げた場合に、
その研究内容を公表するための文書となります。
ただし成果ならなんでもいいのでなく、
「これまで知られていないことを新たに明らかにした」
のような新規性が必要となります。
つまり、
学術論文とは、学問についての新規性を持った研究内容をまとめた文書
と言えます。
しかし実は、
「学問についての研究内容をまとめた文書」は、
学術論文だけではありません。
その内容や目的に応じて、いくつかの種類があります。
それらを知っておくと、
知りたい情報に素早くアクセスできるようになります。
そこで、学術論文、学会抄録、学術雑誌、レビュー、文献などの違いや、
- 信頼性担保の方法
- 新規性の検証方法
- 学術内容の効率的な理解方法
など、論文を読む際に欠かせない知識について、
以下で、わかりやすくまとめました。
忙しい中でも効率的に学術論文など読んでみたいあなたには必ず役に立つ情報となっています。
この先は会員限定になります。
会員の方はログインをお願いいたします。
登録がまだの方は、会員登録をお願いします。
>>> 会員登録はこちら
↓こちら無料で読めます