ウイルスは、生き物のように振るまう物質のことです(と考えられています)。
人類はこれまでの歴史の中で、 ウイルスによって、数十年に1回程度、生活に大きな影響を受けてきた経験があります。
現在はまさにその状況だと考えられます。 様々な情報に触れるうちに、
- なぜ、そうなの?
- 本当に、そうなの?
- 結局、私たちはどうすればいいの?
と思われる方も多いのではないでしょうか。
まずは政府や専門家からの行動指針を守ることが重要です。
しかし、生活していて
- この場合はどうすればいいんだろう?
といった指針にはない場面に出会うことも多いのではないでしょうか。
生活の中で、その都度、妥当な判断をする力が自分や周りの身を守ることにつながります。
とはいっても、
- 妥当な判断ってどうすればいいの?
と思われる方も多いかと思います。
ネットなどで調べても、情報が錯綜し、玉石混交の場合もあり、 不必要に不安を煽る情報が多いこともあります。
よく調べることができる方ほど、
- 専門家でも意見が違う場合があったり、
- 国や地域で違ったり、
- ウイルス以外のこととの関連
など、様々なメリット・デメリットの相反する状況に、辟易されることもあるかもしれません。
そしてそれらに深入りすることで、
- 疲れてしまう
といったことも多いのではないかと思います。
一般人の私たちに必要なのは、専門家レベルの知識ではないかもしれません。
必要なのは、以下の2つです。
- 教科書に載っているような、情報が確実な基礎知識の理解
- その基礎知識を使い、新たな情報を読み解く力
の2点です。 正しい知識を持ち、活用できることで、
- 不安を減らせる
- デマから身を守れる
- 行動を妥当なものにして、自分や周囲を助けれる
ことができます。 とはいっても、
- ウイルス情報を読み解く
ための
- 基礎知識ってなに?
と思われる方も多いかと思います。
そこで本記事では、
- ウイルスってなに?生き物なの?
- ウイルスと細菌の違いや大きさとは?
- ウイルスの基礎知識をサクッと身につけるには?
といったことがサクッとわかるおすすめの本をご紹介します。
これらを学ぶことによって、日々の生活で、
- この場合、どうするのがいいの?
といった疑問に自分で妥当な判断をできるようになり、 自分だけでなく、ご家族を守れます。
また、ウイルスへの予防や対策についての知識は、一生モノです。
短期的にも、長い目でみても必ず役立ちますので、
ぜひ
- 1日1項目
など、自分のペーズで知識を蓄えていくことがオススメです。
本記事の概要
「ウイルス」ってなに?ウイルスは生物?ウイルスと細菌の大きさや違いとは?ウイルスから身を守るための基礎知識を得たいあなたにおすすめの本はこちらをどうぞ
「ウイルス」とは
ウイルスとは、とても小さな物質です。
レゴブロックのように、 多くのブロックが組み合わさって 球や正20面体などの形をしています。
その中に核酸を持っています。
ウイルスによって、ブロックを脂質の膜で囲んでいるものや、
ブロックの中に脂質の膜を持っているものがあります。
ウイルスの英語とその読み方は
英語で 「Virus」と書きます。
ラテン語がの”粘液”が語源となっています。
読み方は「ヴァィラス」と発音します。
ウイルスは生き物なの?
生き物の定義にもよりますが、生物でないと言われています。
ウイルス自体は、自分で増殖できないからです。
しかし、ウイルスを作っている材料は、私たちの体と同じもの(タンパク質や核酸、脂質など)です。
なので生物だと考える場合もあります。
生物と非生物の中間的な存在と言えます。
ウイルスと細菌の違いって?
ウイルスと細菌はどちらも病気の原因になるものです。
ウイルスは、自分だけでは増えることができません。
細菌は、自分だけで増えることができます。
なのでウイルスは非生物的で、細菌は生物と考えられます。
またウイルスと細菌の大きさを考えると違いもはっきりします。
ウイルスや細菌の大きさどのくらい?
ウイルスも細菌もとても小さいです。
ウイルスの大きさは、細菌の大きさを経由するとイメージがわかりやすくなるかと思います。
まずは、ウイルスと細菌の大きさの違いを説明しますね。
ウイルスの大きさは?
ウイルスは、細菌のだいたい1000分の1くらいの大きさになります。
と言ってもイメージがわきにくいですよね。
例えば、ウイルスを野球ボールとすると、 細菌は野球場全体といった感じです。
なので、ウイルスはとても小さく、細菌はウイルスよりだいぶ大きいわけです。
ちなみにですが、 ウイルスは小さいので、 より大きな細菌に感染するものがいたりします。
細菌の大きさは?
今度は、細菌を野球ボールくらいと考えると、 野球場は、ゴマの1粒くらいになります。
私たちからすれば、ゴマの1粒はとても小さいですが、
その1000分の1くらいが細菌の大きさになります。
そしてウイルスは、細菌の大きさのさらに1000分の1くらいとなります。
なので、ウイルスは目で見ることはできず、電子顕微鏡などで観察することになります。
ウイルスと電子顕微鏡
ちなみに、千円札にもなった野口英世ですが、 黄熱病の研究中に亡くなりました。
野口英世は黄熱病の原因となるものを見つける研究をしていました。
野口英世が使っていた顕微鏡は「光学顕微鏡」で、 細菌を見ることができます。
しかし「光学顕微鏡」ではウイルスを見ることができません。
ウイルスを見るためには「電子顕微鏡」が必要です。
当時はウイルス自体が知られていなかったという事情があります。
野口英世は未知の病原体への献身的な研究を行っている途中でウイルスに蝕まれたわけです。
こういった研究の積み重ねによって、 黄熱病の原因は現在ではウイルスであることがわかり、
黄熱病は恐れる必要のない病気になっています。
というわけで、ウイルスについての大まかなイメージはつかんでいただけたのではないでしょうか。
ここからは、ウイルスについてより具体的に学べるおすすめ本をご紹介します。
ウイルスの基礎知識をサクッと学べるおすすめの本
ウイルスの基礎知識本をご紹介する前に、 コロナウイルスの対策・予防の分かりやすい本をご紹介したいと思います。 (これらの知識は基礎として有用ですが、 政府や地方自治体の指針や、かかりつけ医の診断やアドバイスなどを最優先されてください)
世界一わかりやすい 新型コロナウイルス完全対策BOOK
とにかくサクッと重要なポイントを学びたいあなたにおすすめの1冊です。 (第1章) ウイルスの基礎知識の要点 感染の仕方、 ウイルスの生きている時間などを学ぶことで予防や対策のやり方の意味がわかるようになります。 (第2章) ウイルスの予防と対策 正しい手洗い、マスクの使い方、免疫力を高める週間などの予防方法を理解でき、正しい対策をすることができます。 (第3章) ウイルスの症状が出たらどうするか 咳や発熱が起きた時の対処法やチェックシートがあり、連絡先などが一覧としてまとめられています。 また、何かと不安なことも多いかと思います。 本書では不安とその対処法がQ&Aとしてまとめられており、不安の解消ができます。 本書はウイルス対策をサクッと60分で学べるお忙しいあなたにもおすすめの1冊となっています。 同様のコンセプトとして、こちらの本もございます↓新型コロナウイルス肺炎、インフルから身を守れ! (安心4月号増刊)
報道などでは、日々様々な切り口から新しい情報が流れてきます。 ウイルスを知るだけでなく、社会としてどう考えるかなど、異なる観点から学んでおくのが役立ちます。 そういった場合にオススメな1冊はこちらです↓「新型コロナウイルス」―正しく怖がるにはどうすればいいのか―
本書は、個人個人がウイルスの感染予防や治療などの正しい理解ができるだけでなく、 中国での感染状況の詳細やその社会的背景を通じて、 それらの情報から日本が社会としてどのようにウイルスと闘うべきかという「防疫」の観点も学べます。 感染症対策の専門家たちは何を重視しているのかといった一般の方とは違った見方について理解できます。 個人としての対策だけでなく、社会としてのウイルス対策を学べる1冊と成っています。 サイエンスの観点からは、こちらもオススメです↓日経サイエンス2020年5月号(特集:新型コロナウイルス/宇宙の化学進化)
本書では、特集として新型コロナウイルスの特集が組まれています。- 専門家会議のインタビュー
- コンピュータの活用による迅速な研究
といった点がコロナの内容となっています。 これまでSARSやMARSといった感染症の拡大危機がありました。 それらとの違いの1つとして、
- コンピュータを武器にしたウイルスの研究
が挙げられています。
- ウイルスの解明
- 感染拡大の予測
- 治療薬の探索
などの重要な知見を得るのにコンピュータの活用が進化しています。 コロナウイルスのゲノム解析やたんぱく質の立体構造の決定などが素早く行われました。 それにより、治療薬の選定から素早い臨床試験の開始まで、 通常での期間よりも迅速に行えた との点が今回のコロナウイルスでの研究の特徴であったことが解説されています。 その他にも興味深い特集が多数掲載されていてオススメです。 呼吸器内科医の方々による解説書もございます↓
Kindle Unlimited で「無料」で読むならこちらもございます↓
Newsweek (ニューズウィーク日本版) 2020年3/10号新型肺炎 何を恐れるべきか
Newsweek (ニューズウィーク日本版) 2020年3/17号[感染症vs人類]
↑これらはKindle Unlimitedの登録で無料で読めます。 Kindle Unlimitedに登録したことないあなたは お試し登録をしてみてはいかがでしょうか。 (初回30日間、無料で体験できます)ここからは、ウイルスについての基礎知識を学べるおすすめ本をご紹介します↓ 1冊目はこちら【お子様も理解できる、ウイルスのイメージをつかめる、わかりやすい1冊です】
気になるあの病気から自分を守る! 感染症キャラクター図鑑
本書は、インフルエンザやノロウイルスなど、 毎年話題に出てくるような感染症について、 キャラクターを使いながら、親しみやすく解説してくれている1冊です。- 感染すると、体調はどうなるの?
- どうやったら防げるの?どこから感染するの?
- どういう治療があるの?
など、知っておいて損はない知識を、 大人の方だけでなく、お子様もわかりやすく学べます。 お子様と一緒に、親御さんが読み聴かせるなどの使い方もおすすめです。 お子様と過ごしながら、 ウイルスについてや、ウイルスが引き起こす感染症など ウイルスの知識と予防や対策について学べます。 お子様自身がこれから一生自分を守れるようになる知恵を与えてあげるのにも最適な1冊となっています。 2冊目はこちら【ウイルスの基礎知識を絵や画像で視覚的に学べる1冊です】
ウイルスと感染症 (別冊ニュートン)
本書は、図やイラストなどを中心として、 専門的な内容を目で見て理解しやすく工夫された良書です。- ウイルスとは何か?
- 人体にどのように害を与えるのか?
といった基礎知識に加えて、新型インフルエンザウイルス、ノロウイルス、エボラ出血熱やエイズなど、 様々な感染症について、図解で徹底的にわかりすく解説してくれています。 それだけでなく、人体に備わる防御システムである免疫についても基礎知識やワクチンの効く仕組みなどがまとめられています。 目で見ながらパラパラめくるだけで、目に見えないウイルスや、体内で起こっている免疫の働きをイメージできるようになります。 新型コロナウイルスの情報を理解するための基礎知識としても十分役立つ情報となっています。 3冊目はこちら【ウイルスの基礎知識を進化の観点も加えて、わかりやすくサクッと学べます】
新しいウイルス入門 (ブルーバックス)
本書は、ウイルスを学ぶ教科書の内容を、さらにわかりやすく一般向けに解説しなおされた1冊です。- ウイルスの形
- ウイルスの種類
- ウイルスがどこにいるか
- ウイルスの増殖の仕方
- 様々なウイルスと病気の関係
- ウイルスと進化・ウイルスの起源
など、ウイルスのイメージをサクッとつかむことができます。 図やイラストが見やすいので、初めて学ぶ方も学びやすいはずです。 加えて、コラムには、私たちの生活に関係の深い
- ワクチン
- 遺伝子治療
- 私たちの役立つウイルス
などのお話が簡潔にわかりやすくまとめられています。 ウイルスで知っておくと良い内容全体について、サクッと概要をつかめます。 これらの知識を持っておくことで、 ウイルス予防や対策のやり方などの是非を判断する根拠を得ることができるおすすめの1冊です。 同著者は研究者の方で、荒川河口付近で巨大ウイルスを発見され、関連する以下の書籍もございます。
本著者により発見された「巨大ウイルス(トーキョーウィルス)」は、その他のウイルスよりも格段に大きく、 これまで知られていたウイルスよりもさらに生物に近い特徴を備えていることがわかりました。 生物に近い仕組みを持ったウイルスの発見によって、 生物とは?といった私たちの生命観を揺さぶるシリーズとなっています。 ウイルスは生物の進化にどう関わったのか?といったことが学べます。 基礎知識を学ぶならこちらの書籍もございます↓ウイルスは生きている (講談社現代新書)
本書はウイルスの種類や形、核酸などの基礎知識をわかりやすく学ぶことができます。 加えて、ウイルスが生物なのか非生物なのか、生物と非生物の境目についてわかりやすく解説された1冊です。 本書の立場はウイルスは生き物である、として、その根拠となる内容がまとめられています。 ウイルスというと悪いイメージを持たれる方も多いかもしれません。 しかしウイルスはヒトなど他の生物と共生しており、他の生物の進化の立役者である場合があります。 ウイルスのおかげで、哺乳類が進化できたといったお話もあり、私たちの起源にウイルスが関与していたことを学べます。- 生命とは何か?
といった深い話へいざなってくれます。 ウイルスの見方を変えてくれる1冊となっています。
というわけで、
本記事では、
- ウイルスってなに?生き物なの?
- ウイルスと細菌の違いや大きさとは?
- ウイルスの基礎知識をサクッと身につけるには?
といったことがサクッとわかるおすすめの本をご紹介しました。
まだまだおすすめ本はありますので、随時更新していきたいと思います。
よかったらSNSなどフォローしてもらえると見逃さないかと思います。
こちらもございます↓
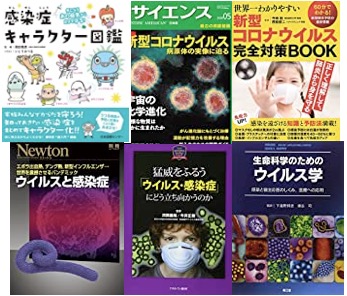




![Newsweek (ニューズウィーク日本版) 2020年3/10号[新型肺炎 何を恐れるべきか]](https://m.media-amazon.com/images/I/51ObESbNZ6L._SL160_.jpg)
![Newsweek (ニューズウィーク日本版) 2020年3/17号[感染症vs人類]](https://m.media-amazon.com/images/I/5136gKQkQEL._SL160_.jpg)






















