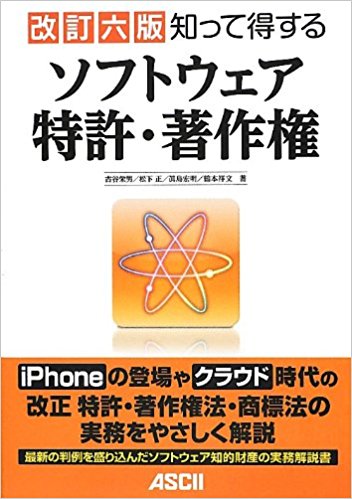マーケティングで重要なのは顧客を知ること、とよく言われます。
顧客の視点に立ち、いかに「付加価値を提案」できるかが勝負の分かれ目です、
他社との違いは何なのか?どこが優れているのか?を顧客に理解してもらうことで自社の優位性を確保できます。
でも、どうやって顧客を知ったらいいのでしょうか?
また、多くの企業では「現場の生産性」を上げることを重要な課題にあげています。
社長さんをはじめ、管理職の方々は、現場で働く社員たちを「観察」することが1つのポイントになります。
社員一人ひとりの暗黙知を、目に見える形式知に変えることで、優秀な社員のノウハウを他の社員たちに共有することが可能になります。
では、どうやって現場を観察したらいいのでしょうか?
こらら2つ、顧客や現場の「行動観察」が今回のテーマです。
本記事の概要
顧客や現場を知るには、見る(see)でなく観察(observe)すること
人間の行動は、アンケート調査のようなその人が既に意識している情報だけで理解できるわけではありません。アンケートを書いた本人ですら気づいていない、水面下の情報によって行動が決まっている可能性もあるからです。
顧客の購買行動を例にすると、「なぜその商品を買ったのか?」というアンケートをとれば、何歳の男性もしくは女性が、どこで、どの商品を、なぜ買ったのか、というデータが得られます。これは確かに次の商品開発に役に立つかもしれません。
しかしこの情報は、
「すでに顧客自身が分かっている情報」
が現れてきているにすぎません。
ワーキングマザーが休日の昼過ぎに、昼食を与えたにも関わらず、子どもを連れてマクドナルドに食べに行く、というのは、マクドナルドが好きだからかもしれません。
でも実は、普段働いていて子どもの相手をできない「うしろめたさの裏返し」かもしれないわけです。こういった感情は本人もあまり意識していないこともあり、アンケート調査に素直に現れてくるとは限りません。このように、
人間の行動は、表面に現れたもののみならず、
水面下に隠された情報も非常に重要になります。
表面的な行動をみる(see)だけでは、水面下の様子を知ることはできません。その行動の底にある隠された気持ちを推測しながらみる(observe)ことがとても大事なのです。
このような観察の手法を、「行動観察」といいます。
この行動観察は、多くの企業が直面している
- 顧客を知ること
- 現場の生産性を上げること
という課題の解決に有効な手段です。
顧客や現場社員の行動を観察することで、これまで見えてこなかった改善点が発見できるからです。
「行動観察」で重要な2つのポイントとは?
行動観察するさいに重要なポイントは、以下の2つがあります。
①、必ずナマの現場を、自分の眼で観察すること
現場から上がってきた数値やデータをみて分かるものではありません。
必ず現場に赴いて、行動を見て、それを解釈する、そしてその解決策を考えるようにします。
つまり、「実態を深く知ること」ことが最初の第一歩となります。
②、独りよがりにならず、客観的に根拠ある解決策を提案すること
実態を把握したら、その行動の下に潜んだ理由を推測します。そのためには仮説を立てる必要があります。
「○○だから、こういう行動なんじゃないか?」
というやつです。この○○が仮説で、この部分が観察者から出るアイデアとなります。
「AだからB」というときに、この関係を「因果関係」といいます。
行動観察では、この因果関係は自分の経験や勘で考えない、というのが注意点です。
勘や経験はもちろん軽視すべきではないですが、行動観察のプロセスではそれらは排除します。そしてきちんと「客観的に分かっている事実」をもと因果関係の仮説を組み立てます。
論理的に説明できることが重要で、そうであれば再現することができ、ノウハウとして蓄積していくことが可能となるからです。
「行動観察」では、仮説を立てる能力が重要
因果関係を推測するときには、すでにわかっている客観的事実を基に仮説を組み立てるといいました。
ということは、客観的な事実をより多く知っている方が、仮説を立てやすくなりますよね。たくさんの可能性を考えることができるからです。
というわけで、行動観察で仮説を立てる際に役に立つ客観的事実を学びたいあなたは、以下の学問がありますので、参考にされてみてください。(最後におすすめ本も紹介しておきました)
人間工学
たとえば以下のように、ヒトにはできる・できないに一定の範囲があります。
- 年齢とともに、筋力が低下する(持てる重さは変動する)
- ヒトの短期記憶では一度に覚えれる数字の数は限られている
そういった事実を取り入れながら観察するのが有効です。
エスノグラフィー(フィールドワークとも呼ばれる)
対象とする顧客(個人)や企業の価値観や習慣、文化や風土などをありのままに調べることをいいます。ターゲットとなる顧客に密着する形でその様子をつぶさに観察したりして、そこから隠された理由などを考えたりします。
環境心理学
人間の行動は、意外に気づかないですが、温度や湿度、音や光といった周囲の環境によって大きく影響を受けています。例えば、「ヒトとヒトが助け合う」という行動は、いつでもどこでも同じだと思われるかもしれませんが、静かな部屋の方が助け合いは高まり、うるさい部屋では少なくなる、ということが知られています。このような環境による人間の性質の変化も考慮することが仮説を磨いて行く際にも重要となります。
社会心理学
ヒトは社会的な生き物です。他者との関わりの中で自己を理解したり行動を決めたりしていきます。そういったヒトとヒトの相互作用の中で、どんな関係によってどんな影響が出たのか?といったことを考える際に社会心理学の知見が役に立ちます。
表情分析
表情は感情を映す鏡と考えることができます。喜びや悲しみ、怒りや憎しみ、驚きや軽蔑といった感情は、表情を通じて理解することが出来ます。また、この表情は日本人特有でもなく、世界共通のものであることも分かっています。人類共通のコミュニケーションツールである表情をつぶさに観察することで、そのヒトや集団の感情を理解する手助けとなります。
こういった分野で明らかになっている事実を知っておくことで、より多くの良質な仮説を立てることができるわけです。
- 行動分析って役立ちそうだなぁ〜
- 自社の課題でも活用してみたいなぁ
- でもどうやったらいいんだろう
- まずはサクッと全体像をつかんだり、具体例をみてみたいなぁ
なんて思われた方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、行動観察の専門家が、全体像をサクッと理解させてくれるおすすめ本をご紹介します。
[amazonjs asin=”406288125X” locale=”JP” title=”ビジネスマンのための「行動観察」入門 (講談社現代新書)”]本書は、行動観察をやってみたいけどよくわからないなぁ〜という初心者のために、
- 行動観察のイロハ
- 9つの多様な具体例
- 行動観察する際に気をつけるポイント
など、短時間でなるほど〜、こういうことなんだね!と理解させてくれる1冊です。
本書の構成は以下の通りです。
はじめに
第1章 行動観察とは何か?
2つのポイント
付加価値の提案
生産性の向上
行動観察の3つのステップ
行動観察が有効な理由
第2章 これが行動観察だ
1、ワーキングマザーの隠れた欲望
2、人でにぎわう場の作り方
3、銭湯をもっと気持ちのいい空間に
4、優秀な営業マンはここが違う
5、オフィスの残業を減らせ
6、飲食業を観察する
7、達人の驚異の記憶術に学ぶ
8、工場における生産性向上と品質向上という古くて新しいアプローチ
9、元気の出る書店を作ろう
第3章 行動観察とは科学である
科学と同じ手続きを踏む
大切なのは、仮説を生み出すこと
自分の価値観から自由になる
人間についての知見を持つ
行動観察を短期間で身につけるにはどうすればよいか?
行動観察による学び
おわりに
となっています。
行動観察の基本をつかんでから適応例を読むことで、自分でやってみる際のヒントになるように工夫されています。行動観察例の中で「ここはこうすればよかったと思い、こう改善した」といったように、読者も陥りがちな間違いを具体例を通じて示してくれています。
ヒトの行動をつぶさに観察するので、行動観察の手法を学べるだけでなく、日常関係のある事柄について、これまで思ってもいなかった気づきを与えてくれます。具体例を読んでいるだけでも、ヒトの行動の理由の一端に触れることができ、とても勉強になります。
行動観察の方法を学びたい方に加えて、具体例を読んでみるだけでも、マーケティングや社員の気持ちの理解に役立つのではないかと思います。おすすめです。
行動観察での仮説構築のために学んでおくと役に立つ分野のおすすめ書籍です↓
こちらの記事もございます↓
『「マーケティング」を科学的に行いたいあなた、フリーソフト「R」を使った「データ分析」はいかがでしょうか【マーケティング・データ分析の基礎:Useful R】』
『定性調査を活かしてマーケティングを強化したいあなたはこちらをどうぞ【消費者理解のための 定性的マーケティング・リサーチ】』