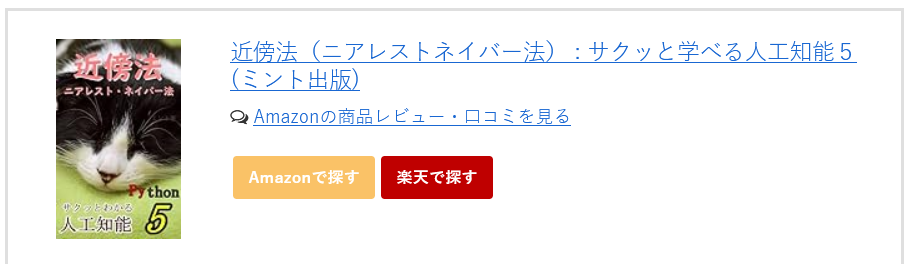データ分析の世界で、「まずは手軽に試せるけど意外と奥深い」と評判なのが k近傍法(k-Nearest Neighbors, kNN)です。
難しいパラメータはほとんどなく、直感的にイメージしやすい一方で、実務でしっかり使いこなすには意外なコツがあります。
本記事の概要
1. k近傍法とは?
与えられた未知サンプルに対し、学習用データ空間内で「たった今」最も近いk個の点(近傍)を探し出す。
その近傍のラベル多数決(分類)または数値の平均(回帰)で答えを推測するシンプルな方法です。
ユークリッド距離だけでなく、マンハッタン距離、コサイン類似度など、問題特性に応じて切り替え可能となっています。
– 小さすぎる k
ノイズに敏感になり、過学習を起こしやすい(例:k=1 は最も不安定)。
– 大きすぎる k
なだらかな境界を描きすぎて、カテゴリーの細かな違いを無視するリスク(過小適合)。
– 経験的チューニング
クロスバリデーションで最適な k を探すのが定石。
– 線形スキャンの重さ
毎回すべてのサンプルに距離計算を行うと、データ数が数万を超えたあたりからレスポンスが厳しくなる。
– 高速探索技術
KD-Tree、Ball-Tree、Approximate Nearest Neighbor(Annoy, Faiss)などを用いてスケーラビリティを確保することができます。
2. どんな場面で活用されている?
kNNの強みは、モデル構築が不要、直感的な振る舞い、汎用的に使える点などにあります。
(1). レコメンデーション
ユーザー同士、またはアイテム同士の類似度計算に基づく協調フィルタリングに使えます。
(2). 異常検知
正常サンプルの近傍距離分布を学習し、異質な点をアウトライヤーとして検出。
(3). 手書き文字認識
ピクセル単位で距離計算し、「見慣れた数字」に分類。
(4). 医療診断支援
患者データの類似サンプルを探し、過去症例の治療結果をもとに判定補助。
(5). 画像検索エンジン
特徴ベクトル化した画像間の距離で「似ている写真」を抽出。
実は、分類にも回帰にも使えて、距離の定義や先進的なインデックス手法を組み合わせることで応用範囲が一気に広がります。
3. k近傍法を学ぶメリット
– データ間の類似度を定量化する思想は、クラスタリングや距離ベースの異常検知、さらにはカーネル法にも応用可能です。
– たった数行 のコードで動作を確認でき、前処理やモデル評価の流れを手軽に学習させられます。
– ハイパーパラメータ調整(k や距離尺度)による精度変化を直感的につかめる。
– 大規模データを扱う現場で必須となる 空間データ構造を習得できる。
– 近似探索ライブラリを使った高速化は、レコメンデーションやビッグデータ分析で重宝されます。
– 単純なkNNが理解できれば、距離学習や局所線形モデルの応用にスムーズに移行できる。
k近傍法(ニアレストネイバー法)を学びたいあなたには、こちらの書籍がおすすめです
近傍法(ニアレストネイバー法) : サクッと学べる人工知能5 (ミント出版)
その他の出版本はこちらからどうぞ