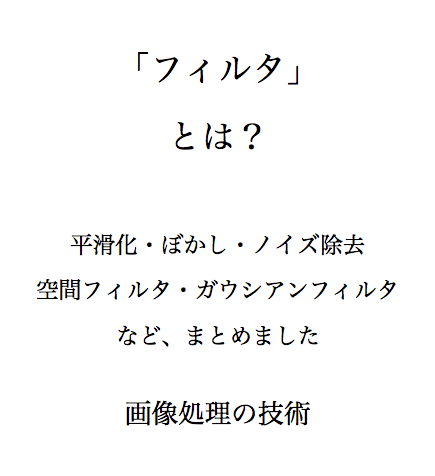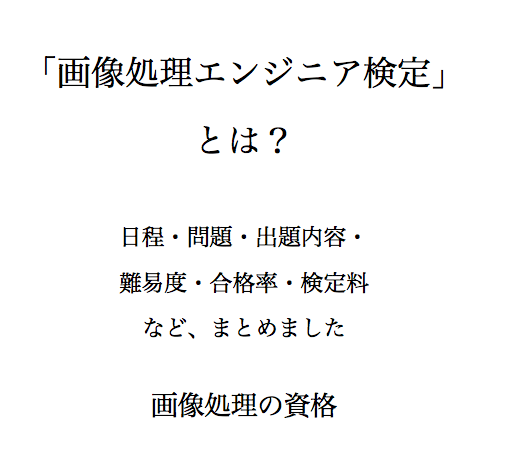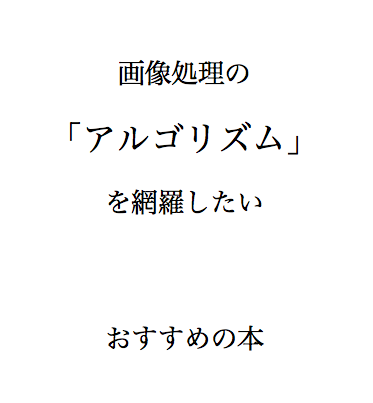画像処理の技術には、画像の修正を行ったり、ノイズを除去したりする
「フィルタ」という方法があります。
気に入った景色、友達との記念写真など、スマホやデジカメで撮ることもあるかと思います。
手軽に撮影できる反面、手ぶれしたり、顔が暗く写ったりと、
納得いく写真が撮れないこともあるかと思います。
こんな時デジタル画像なら、画像処理を行うことで、
- 明るさを調節したり
- ぼけを修正したり
- ノイズを消したり
サクッと画像の修正をすることができます。
画像処理で修正することで、後からでも、より良い写真に変えることができるわけです。
画像の修正処理技術の1つが「フィルタ」になります。
フィルタは
- 画像処理アプリや Photoshopなどの画像編集ソフトについて、ここはフィルタを使って処理しているな、などのように中のアルゴリズムを理解しながら活用できる
- 精密な画像解析を行うための、画像のクリーニングができる
- 画像認識など人工知能技術の入力となる特徴量をより良いものにできる
といった場面で応用・活用されており、学ぶメリットも感じてもらえるかと思います。
そこで本記事では、画像処理のフィルタの1つ「空間フィルタ」について、
- 画像処理を基本から学びたい
- 画像処理関係の仕事や就職、転職やアルバイトに備えたい
- 画像処理の知識を活用できる人工知能などの分野の基礎を作りたい
といったあなたのために、
空間フィルタの基本的な仕組みから、その方法、手法の種類などを、わかりやすくまとめました。
本記事の概要 [表示]
【画像処理の基礎技術2】「フィルタ」とは?画像の改善、解析、認識をやりたいあなたのために、空間フィルタリングの方法などをわかりやすくまとめました
上では、フィルタについて、空間フィルタといったのですが、別に、周波数フィルタというものもあります。
どちらも発想は同じですが、具体的な仕組みについては違いますので、ここでは区別しています。
周波数フィルタについても、他の機会に説明したいと思います。
フィルタとは、空間フィルタの基本知識と方法(Spacial filter)
- 画像をよりよくしたい!
- 見栄えのいい画像に変えたい
といった場合には、
- 明るさを変える
- コントラストを変える
といった方法があります。
明るさやコントラストの情報は、デジタル画像の場合、画素(ピクセル)1つずつにデータが収められています。これを「画素値」と呼びます。
なので、明るさやコントラストを変えたければ、画像のそれぞれの画素値を変えればいい、というわけです。
そして、画素値の変え方には、大きく分けて、2通りのやり方があります。
1つ目は、1つの画素ごとに単独で変える方法です。
この方法では、入力した画像のそれぞれの画素値は、
階調変換関数(トーンカーブ関数)などを使って、単独で別の画素値に変えられます。
2つ目は、1つの画素の情報(画素値)を、周りの画素の画素値を考慮した上で変える方法です。
ある画素値を変える時、周りの画素値の情報も使う、というわけです。
この方法がフィルタを使う手法で、今回のメインになります。
というわけで、以下では、
- まわりの画素値を考慮するってどういうこと?
- フィルタにはどんな種類があるの?
- それらの特徴や応用例は?
といった内容を、1つずつ丁寧にわかりやすく解説しています。
この先は会員限定になります。
会員の方はログインをお願いいたします。
登録がまだの方は、会員登録をお願いします。
>>> 会員登録はこちら
こちら無料で読めます↓